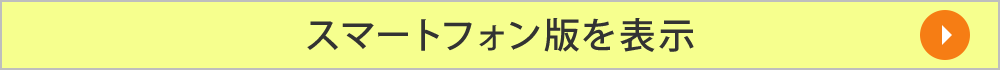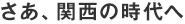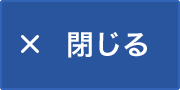KANSAI伝統文化EXPO
大阪・関西万博の来場者に向けて、関西の魅力を広くPR し、万博をきっかけに関西各地への周遊を促進することを目的に、「KANSAI 伝統文化EXPO」を開催します。
古くから継承されてきた歴史や風土に根差した関西の伝統芸能7団体による実演ステージのほか、 民俗芸能体験や民俗芸能に関連した映像の上映など、関西文化の魅力を発信するイベントを実施します。
日時
令和7年8月9日土曜日、8月10日日曜日、8月11日(月・祝)
※各日の開始時刻は下表のとおり
会場
大阪・関西万博 関西パビリオン多目的エリア(大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目)
料金
無料・予約不要(万博会場への入場料は別途必要です。)
内容
・関西広域連合構成府県市の民俗芸能による実演ステージ及び民俗芸能体験を実施
・民俗芸能に関連した動画も併せて上映
| 開催日時 | 出演団体 | 構成府県市 | |
| 8月9日土曜日 | 11時00分~ | 阿波十郎兵衛座 | 徳島県 |
| 13時30分~ | 交野ケ原交野節・おどり保存会 | 大阪府 | |
| 16時00分~ | 冨田人形共遊団 | 滋賀県 | |
| 8月10日日曜日 | 11時30分~ | 大蔵谷獅子舞保存会 | 兵庫県 |
| 15時00分~ | 藤白の獅子舞保存会 | 和歌山県 | |
| 8月11日(月・祝) | 11時30分~ | 宇治田楽まつり実行委員会 | 京都府 |
| 15時30分~ | 篠原おどり保存会 | 奈良県 | |
| 映像 | 出演者 |
|
民俗芸能に関するインタビュー映像
民俗芸能に関わる方々が、 現状と課題、継承のための方策など、 民俗芸能への想いを熱く語ります。 |
・徳島県立阿波十郎兵衛屋敷館長 佐藤憲治 氏 ・京都六斎念仏保存団体連合会会長 秋田吉博 氏 ・因幡麒麟獅子舞の会会長 吉澤敏彦 氏、山本修 氏 ・株式会社オマツリジャパン代表取締役 加藤優子 氏 ・一般社団法人マツリズム代表理事 大原学 氏 ・國學院大學客員教授・坐摩神社権禰宜 橋本裕之 氏 |
出演団体の紹介
阿波十郎兵衛座
昭和54年(1979年)に阿波十郎兵衛屋敷内に人形浄瑠璃上演舞台が建てられたのを機に、宮島地区の女性ばかりで座を結成。同年4月の初舞台以来、屋敷専属の人形座として、年間平均350回の公演を行ってきた。昭和60年(1985年)の大鳴門橋開通から昭和63年(1988年)の瀬戸大橋開通の頃がピークで年間626回を数えた。平成18年(2006年)からは阿波人形浄瑠璃振興会の一座として上演している。「傾城阿波の鳴門順礼歌の段」「壺坂観音霊験記」に加えて、平成14年(2002年)には「恵比寿舞」を新たなレパートリーとした。

交野ケ原交野節・おどり保存会
現代の「河内音頭」の源流とも言われる「交野ケ原交野節」は、現在の大阪府の枚方市と交野市にまたがる交野郡で誕生し、最も古い説では南北朝時代に南朝方の楠 正行の軍勢が戦に敗れ、この地まで落ちのびた楠軍の軍師が戦死者を手厚く弔った際の念仏踊りが村人によって踊り継がれたと言われる。令和5年(2023年)には大阪府無形民俗文化財に指定された。

冨田人形共遊団
昭和32年(1957年)に滋賀県の記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財に選択された「冨田人形浄瑠璃」は、郷土の誇る民俗芸能として独特の風格を備え、「冨田のデコ」として愛好されてきた。
「冨田人形共遊団」は昭和54年(1979 年)、滋賀県長浜市北冨田に居住する人を中心に市内外の人形を愛好するメンバーにより新生冨田人形共遊団として発足。人形遣い、三味線弾き、語りの太夫の3 業の稽古を日々行い、人形浄瑠璃の保存伝承に励むと共に、地元の小中学生や地域住民、海外からの学生を迎えサマープログラムとして後継者育成、文化の国際交流にも努めている。令和4年(2022年)「全国地域伝統芸能大賞」など数々の賞に輝いている。

大蔵谷獅子舞保存会
大蔵谷の獅子舞は安政2年(1855年)から続いている伝統芸能。 現在は二十余りの芸が伝承されており、雄々しく荒々しい芸風が特徴。獅子舞に付属する構成員や鳴り物などが一体となり、はじめて芸が完成する。 はじめと終わりの芸は決まっているがそれ以外の芸の順番は決まりがない獅子舞演舞となっている。

藤白の獅子舞保存会
昭和41年(1966年)に和歌山県指定無形民俗文化財に指定された「藤白の獅子舞」は、五人立ちの獅子で大きな胴幕の中に舞い手が一列に並ぶように入り、優雅に舞う。熊野九十九王子(くまのくじゅうくおうじ)のなかでも別格である五体王子の一つとして知られる藤白神社の秋祭りに奉納される獅子舞で、笛と太鼓に合わせて、金色の獅子が頭を振りながら猿田彦命(さるたひこのみこと)と向かい合う。
「藤白の獅子舞保存会」は、昭和41年(1966年)に発足、昭和45年(1970年)の大阪万博でも舞を披露するなど、和歌山県の内外を問わず現在でも積極的に対外公演を行っている。

宇治田楽まつり実行委員会
宇治田楽まつり実行委員会は、「源氏物語」をテーマに宇治市と連携し、まちづくり事業に取り組んでいる。宇治が発祥の地とも言われ、時と共にその姿を失った芸能「田楽」。その復活をテーマに、伝統的要素を取り入れた芸能を創作するプロジェクトを発足し、普及活動を行っている。

篠原おどり保存会
奈良県五條市大塔町に伝わる民俗芸能で、奈良県指定・国選択無形民俗文化財。
踊りは、「式三番」と呼ばれる奉納踊りと、住民たちが楽しみのために宴席などで踊った踊りの2種類に分かれ、いずれも男性が太鼓を、女性は扇を持って踊る。 踊りの様式は戦国時代から江戸初期に流行した「風流踊り」、 歌詞は室町末期に流行した「小歌」が原型となっている。
保存会は、毎年1月、篠原集落にある天満神社に奉納している式三番の3曲とその他14曲の踊りを伝承している。村人の減少で途絶えかけるが、平成 26 年(2014年)公募により保存会が再結成され、積極的に活動中。

各団体の紹介はこちらからもご覧いただけます。
また、関西広域連合広域観光・文化・スポーツ振興局のYouTubeチャンネルに各団体の動画も掲載されておりますので、ぜひご覧下さい。
開催場所

その他
令和7年10月5日日曜日に大阪・関西万博ポップアップステージ南において、「関西の伝統文化と現代の融合」イベントを実施予定です。
主催
・KANSAI感祭実行委員会
(関西広域連合、公益社団法人関西経済連合会、一般財団法人関西観光本部、公益財団法人関西・大阪21世紀協会)
・歴史街道推進協議会