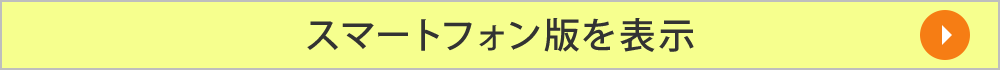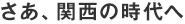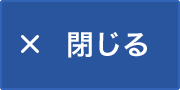久元喜造委員「多死社会における市民の死に寄り添う地方自治体の役割」(令和6年8月23日)
関西広域連合 久元喜造委員(神戸市長)からのメッセージ
「多死社会における市民の死に寄り添う地方自治体の役割」
神戸市長の久元喜造です。
全国的に進行する人口減少の要因には少子化があげられますが、死亡者数の増加も大きな要素です。事実、神戸市の人口減の要因のほとんどが死亡数増による自然減となっています。
そうした中、親族が遺骨の引き取りを拒む場合や相続人が不明な場合など埋火葬を行う人がいない死亡者も増加傾向にあり、その埋火葬は地方自治体が行っています。
関連する事務や費用は地方自治体の大きな負担になっており、神戸市では2023年度634柱の埋火葬を行い、費用は約1,800万円(生活保護法による葬祭扶助を除く)となっています。
身寄りがないと判断された方が残された金品等(「遺留金」という)は、地方自治体に持ち込まれますが、遺留金の保管や活用にも問題があります。
身寄りのない方の埋火葬には遺留金を充て、次に相続人等に弁償を求め、さらに不足する場合は地方自治体が負担することとなっていますが、そもそも遺留金の取扱いにも明確な根拠がありません。
そこで神戸市では、遺留金の歳入歳出外現金としての保管、相続人調査の費用の一部への遺留金の充当等について、2018年度に「神戸市遺留金取扱条例」を定め対応してきました。
その後、国においても身寄りのない人が亡くなった場合の対応についてまとめた手引が策定されました。さらに相続人調査や葬祭費用のための預金引き出しが相続人に優先する旨の金融機関等への周知、関連法令を根拠に遺留金の歳入歳出外現金として保管できる旨の手引きへの記載等、総務省から関係省庁へ勧告がなされています。
しかしながら、依然として相続人調査や財産管理に関して、遺留金を充当できる範囲が明確でなく、実務に沿った内容となっていません。国による遺留金の帰属先の地方自治体への変更や柔軟な活用の制度化が必要であると考えています。
さらに死亡者数の増加だけにとどまらず、親族間や地域内の交流の希薄化等により、自身の死後に不安を抱く方々も増えています。神戸市では市民と葬祭事業者の契約への立ち会い、定期的な生活状況の確認、亡くなられた際の葬儀・納骨の履行確認を行う「エンディングプラン・サポート事業」を今年度から実施しています。
人口減少時代に入っている我が国において、出生数の減少と同様に、死亡数の増加は、我々が向き合うべき現実です。
今後も、神戸市では、こうした現実に目を背けることなく、人口減少社会に適応した様々な施策を展開していきたいと考えます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
関西広域連合本部事務局企画課
〒530-0005
大阪市北区中之島5丁目3番51号
大阪府立国際会議場11階
電話番号:06-4803-5587 ファックス:06-6445-8540本部事務局企画課へのお問い合わせはこちら