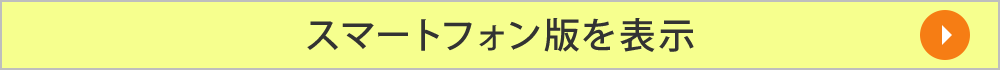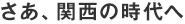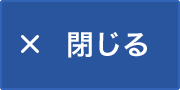関西の食文化 - 郷土料理 -鳥取県-
どんどろけめし

「どんどろけめし」は、油で炒めた豆腐を混ぜた炊き込みご飯です。
「どんどろけ」とは県中部の方言で雷のこと。豆腐を炒めるときのバリバリという音が雷に似ていることから、この名前がついたそうです。
いただき

大きな油揚げの中に生米、生野菜を詰め、だし汁でじっくりと炊き上げた山陰の代表的な田舎めし。
かつては、漁師や農家の人々がお弁当に持って行ったと言われています。
大きなお口でガブリと頬ばれば、ジュワ~ッと広がる甘味と旨味に思わずみんなが笑顔になります。
大山おこわ

大山山麓の食材を使用したしょうゆ味のおこわで、県西部地区の郷土料理です。
使用する食材は家庭により様々ですが、山菜や野菜、鶏肉、所によっては竹輪を入れる地域もあります。
昔、僧兵が戦場に行く時に戦勝を祈願して山鳥と山草を入れた米飯を炊き出したのが始まりと言われ、その後祭りや祝い事のごちそうとして受け継がれてきました。
明治時代には、大山寺の博労座で開かれていた牛馬市で各地から集まった人たちの食事や大山参りの弁当としても親しまれていたと言われています。
また、「大山おこわ」と言われるようになったのは明治以降のことで、以前は旧汗入(あせり)郡名に由来してか、「汗入(あせり)おこわ」と呼ばれていたそうです。
小豆雑煮

お正月の雑煮は地方色豊かで、全国各地ではいろいろな物が食べられているようですが、鳥取の雑煮は小豆の煮汁に柔らかく煮た丸餅が入ったものです。
煮汁がたっぷり入ったものから、小豆がごろごろしていて煮汁は少しというのもあれば、砂糖で甘くしたものや、塩味を効かせたものもあります。
しかし、県下全域で小豆雑煮が食べられているかというとそうではなく、山間部ではしょうゆ味や味噌味が多いようです。
するめいか糀漬

スルメイカの天日干しを調味料と糀で混ぜ合わせるだけの、いたってシンプルな郷土料理です。
山陰地方の山間部で雪に閉ざされた真冬の保存食として生まれ、酒の肴や食事の付け合わせにもよく合います。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
関西広域連合広域産業振興局 農林水産部
〒640-8585
和歌山市小松原通1丁目1番地
和歌山県農林水産部 農林水産政策局農林水産振興課内
電話番号:073-432-0151 ファックス:073-433-3024広域産業振興局 農林水産部へのお問い合わせはこちら