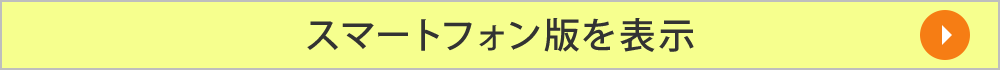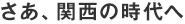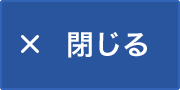関西の食文化 - 郷土料理 -和歌山県-
めはりずし

もとは熊野地方の山仕事の男たちの弁当として作られていた郷土食。
にぎり飯を作り、塩漬けの高菜の葉で包んだ寿司です。
あまりに大きいので、食べるときに目を張るほど大きな口を開けなければならないことからその名が付けられたと言われています。
高菜の漬物の味がご飯にマッチして、食欲をそそります。
茶がゆ

和歌山県の食文化の一つとして、茶がゆを食べる習慣がありました。
耕地に恵まれなかった紀州では、少量のお米でも満足感を得られる茶がゆが常食として食べられていました。冬は暖めて食べ、夏は冷たいまま食べることもあります。
小腹が空いたとき、梅干しや漬物などを添えて、軽く茶がゆを食べるというスタイルで古くから親しまれてきました。
梅干し

和歌山県の梅栽培の歴史は古く、江戸時代に紀州田辺藩が農民にやせ地を利用して栽培を奨励したのがはじまりであり、現在、日本一の梅の産地となっています。
梅の実は5月~7月に収穫され、8月ごろには各農家で一粒ずつ丁寧に天日乾燥され、紀州の美味しい梅干ができあがります。
梅干に多く含まれているクエン酸は、疲労回復、スタミナ保持などの効果があり、現代の健康食としてますます需要が高まっています。
鯨料理

和歌山県の太地町は、古式捕鯨発祥の地として名高く、1606年、この地の豪族和田頼元が組織的な捕鯨を始めたとされています。
古くから日本人に食べられてきたクジラは、低カロリーで低脂肪、そして美味しいクジラのお肉は、カロリーを気にせず食べられる食材です。
柿の葉寿司

塩サバを薄くそいで、一口の大きさに握ったすし飯にのせ、柿の葉に包んだ押しずしにしたもの。昔は、農繁期の手伝いのもてなしとして食べられていましたが、今では正月や祭りの行事食のほか、一般的にも食べられるようになり、現在ではサケなどもネタとして使われるようになりました。
柿の葉の香りは良く、また殺菌効果があるといわれており、包むことにより保存にも適しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
関西広域連合広域産業振興局 農林水産部
〒640-8585
和歌山市小松原通1丁目1番地
和歌山県農林水産部 農林水産政策局農林水産振興課内
電話番号:073-432-0151 ファックス:073-433-3024広域産業振興局 農林水産部へのお問い合わせはこちら