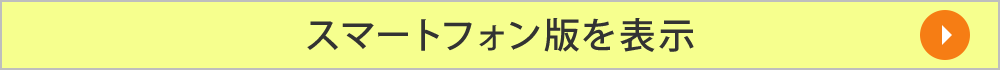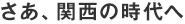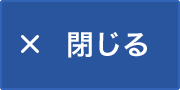関西の食文化 - 郷土料理 -奈良県-
柿の葉寿司

江戸時代中頃から吉野川流域の家々で夏祭りのごちそうとして作られてきました。当時、和歌山方面で水揚げされ塩で締めた鯖を、薄くスライスしてご飯にのせ、身近にあった柿の葉で包み、すし箱に詰めて押しをかけるという手法が生み出されました。
その当時の柿の葉寿司は、乳酸発酵による「生なれすし」(発酵期間:数日~1ヶ月)でしたが、保存技術や輸送技術が発達し、現代の柿の葉寿司は「早なれすし」に変化しています。今では、奈良のお土産として大変人気がありますが、早なれすしの柿の葉寿司も僅かながら、古くからの家々でハレの日の食として受け継がれています。
奈良漬

奈良漬の原型とも言える粕漬の歴史は古く、平城京跡で見つかった木簡には「加須津毛瓜(かすづけ うり)」と記したものがあります。
奈良漬は、酒かすを何度も替えながら漬け込むことで、独特のべっこう色になり、日本酒の香りやうま味が野菜に染み込んでいきます。現在のような漬け方が確立されたのは、室町時代に奈良で酒造技術が発達し、漬け床の酒粕がお酒の副産物としてできるようになったことが大きく、奈良での酒造の進歩がなければ、奈良漬は生まれていなかったかもしれません。
漬ける材料は、シロウリ、キュウリ、守口大根、ハヤトウリのほか、最近では、ニンニク、セロリ、アボカドなど、バリエーションも豊富になってきています。
葛粉(吉野本葛)

葛粉は、葛の根に含まれるデンプンを、真冬に冷水で繰り返し精製し、2~3ヵ月乾燥させたもので、添加物を一切含みません。葛デンプン100%の葛粉を「吉野本葛」と呼び、厳冬期に冷水に何回も晒す製法は「吉野晒(よしのざらし)」と呼ばれます。
葛粉は、葛餅や、ごま豆腐、葛湯、葛饅頭、葛切り、料理のとろみ付けなど、料理やスイーツとして幅広く利用されています。
奈良のっぺ

のっぺは、里芋や大根、人参などを使った具だくさんの煮もののことです。
「奈良のっぺ」は、昆布や干ししいたけのもどし汁をだし汁として使った精進料理で、里芋が煮くずれて、自然にとろみがつくのが特徴でもあります。
毎年12月17日に奈良市の春日大社で催される「春日若宮おん祭」のお渡り式に先立ち、15日に、おん祭を執りおこなう大和士(やまとざむらい)らが身を清める「大宿所祭」で大和士や参拝者らに「奈良のっぺ」がふるまわれます。
大和の雑煮

奈良では、豆腐、祝だいこん、金時人参、里芋、丸餅などが入った白味噌仕立ての雑煮で、雑煮の餅を取り出し、砂糖入りの「きな粉」につけて食べる地域が多いです。
入れる具材には、それぞれ謂われがあり、豆腐は白壁の蔵が建つようにとの願いや、一年間、家族円満に過ごせるようにと、餅は丸餅、野菜類も輪切りにして入れます。きな粉の黄金色は、米の豊作を願うともいわれています。
奈良県では雑煮に入れる直径3cm程度の細い大根が、「祝だいこん」として年末に販売されます。
奈良茶飯 (ならちゃめし)

東大寺「お水取り」で行に籠もる練行衆(れんぎょうしゅう)の献立に茶粥とともに「ゲチャ」と呼ばれる茶飯の原点となるものが出されます。
奈良で発祥した茶飯は、それを気に入った旅人が江戸に持ち帰り、奈良茶飯の店を出し、大豆が入り栄養豊富で腹持ちも良かったため、全国各地で広く知られるようになり、明治以降、再び奈良で広まりはじめました。
飛鳥鍋

鶏肉、野菜を牛乳とだし汁で煮込んだ鍋料理です。飛鳥時代に唐から奈良へやってきた使者が乳製品を伝え、天皇へ献上したところ大変喜ばれ、乳牛が宮中で飼育されるようになり、牛乳飲用のはじまりになったといわれています。
当時は貴族の飲み物でしたが、僧侶たちも密かに飲むようになり、そのうち飼っていた鶏の肉を牛乳で煮て、食していたものが「飛鳥鍋」の起源といわれています。時代とともに庶民の間に広がりましたが、牛乳は高価なのでヤギの乳を使っていたとも。
昭和初期に、明日香の名物料理として地域の産品である牛乳を使った現在の「飛鳥鍋」のかたちが考案され、明日香村等の飲食店等で食べることができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
関西広域連合広域産業振興局 農林水産部
〒640-8585
和歌山市小松原通1丁目1番地
和歌山県農林水産部 農林水産政策局農林水産振興課内
電話番号:073-432-0151 ファックス:073-433-3024広域産業振興局 農林水産部へのお問い合わせはこちら