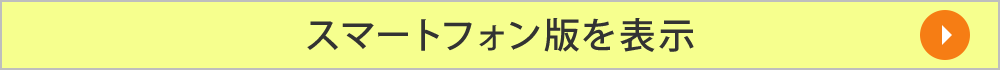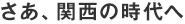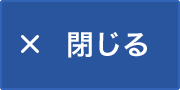関西広域での災害時帰宅支援ステーションの普及・定着
災害時帰宅支援ステーションとは
地震などの大規模災害が発生した場合、通勤や通学、買い物、行楽などで外出している人は、交通機関の途絶により自宅に帰るのが困難になります。このような方々を帰宅困難者といいます。
関西広域連合では、2府6県4政令市(三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市)を代表して、コンビニエンスストア、外食事業者等と「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」を締結しています。
この協定に基づいて、災害時の徒歩帰宅者を支援するために「水道水」、「トイレ」、「道路情報などの情報」の提供をしていただける店舗を『災害時帰宅支援ステーション』といいます。
事業概要
災害時帰宅支援ステーション事業概要 (PDFファイル: 145.1KB)
事業者と締結している協定書ひな形
災害時帰宅支援ステーション事業協定書 (Wordファイル: 46.0KB)
災害時帰宅支援ステーション・ステッカー

ステッカーの統一ロゴマーク
(キタクちゃんマーク)
ステーションで支援を受けてうれしい気持ちを表しています。
日本語の他に、英語、中国語、ハングルの3ヶ国語で案内標記をしています。
支援サービス可能な店舗では、店舗入口付近にステッカーを掲出しています。

ステーション・ステッカーの全国への普及
平成16年度より支援協定に取り組んでおりますが、その後、愛知県や関東の九都県市(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・さいたま市・横浜市・川崎市・千葉市・相模原市)、岐阜県、島根県、鳥取県等においても同一のステッカーが掲出されることになり、令和6年7月現在、全国44都道府県に普及しています。
全国で災害時帰宅支援ステーション・ステッカーのデザイン、ロゴマークを統一することにより、住民への啓発、認知度の向上を図ります。
ロゴマーク使用申請
ステッカーの統一ロゴマーク(キタクちゃんマーク)は、申請をいただければご自由にお使いいただけます。
【ロゴマーク使用申請の流れ】
- ロゴマーク使用許諾申請書とデザイン案、会社概要(法人の場合のみ)を広域防災局へ提出
- 広域防災局にて申請内容を確認後、ロゴマーク画像を使用承認書と併せて提供
- 制作完了後、ロゴマークを使用した完成品を広域防災局へ提出
※用途を確認の上、画像データを提供します。ご利用の際は視認性の保つことのできる解像度でのご利用をお願いいたします。
【申請書ダウンロード】
ロゴマーク使用許諾申請書記載要領(PDFファイル:119.3KB)
【ロゴマーク申請書提出先及びお問い合わせ先】
担当課:関西広域連合 広域防災局 広域企画課
メール:bousai_atmark_kouiki-kansai.jp
- 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@(半角)」に直してください。
- メールの件名は「帰宅支援ステーション・ステッカーロゴマーク使用申請について」としてください。
- 申請者が九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)管内に所在する場合は、九都県市地震防災・危機管理対策部会事務局(こちら)へお問い合わせください。
「災害時帰宅支援ステーション」取組みの経過
将来、発生が予想されている東南海・南海地震においては、沿岸部を中心とした関西一円で揺れが津波による被害が発生することが想定されており、その影響で交通機関の途絶が起こった場合に、京都市、大阪市、神戸市をはじめとする都市部への通勤・通学者や観光客をいかに安全かつ速やかに避難させるという災害時の昼間流入人口問題への対応が大きな課題となる。
特に関西地域での政令都市の昼間人口の内、通勤・通学者の流用人口は、京都市約39万人、大阪市約203万人、神戸市約31万人と見込まれ、大規模災害時の帰宅困難による大量の滞留者の発生によりパニック等の二次災害や物資負担等の問題が予想される。
関西地域の官民連携団である関西広域連携協議会では、この問題を関西広域にわたる課題として検討を行い、平成14年5月に「災害時の昼間流入人口問題の解決に向けて」として報告書にまとめて、避難・帰宅計画ルートの設定や、水、トイレ等の支援サービスを提供する帰宅支援施設の必要性について提言した。
その後、平成16年5月には、徒歩帰宅者への「水道水」「トイレ」「道路情報などの情報提供」の帰宅支援サービスについて、コンビニエンスストアやガソリンスタンドをはじめとする民間事業者への積極的な協力を呼びかけるとともに、当該施設が帰宅支援施設であることを広く住民に周知し、関西全体として取組みを促進するため、帰宅支援施設の名称を「災害時帰宅支援ステーション」とし、ステッカーの広報媒体作成にあたっての統一基準についてガイドラインを定め、統一ロゴマーク及びモデル・デザインを作成した。
このガイドラインにもとづき、平成17年2月17日に関西広域連携協議会が関西2府5県3政令市を代表して、関西域に店舗が所在するコンビニエンスストア・外食事業者12社と徒歩帰宅者への水道水、トイレ、道路情報の提供など帰宅支援サービスの提供を内容とする「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」を締結した。
平成19年7月に関西広域連携協議会は他の広域連携団体との統合により、関西広域機構となったが、平成23年度からは、関西広域連合が当該事業を引継ぎ、平成23年9月22日に協定を再締結し、この取組の推進を図っており、令和6年11月現在、コンビニエンスストア・外食レストラン・ドラッグストア等29事業者と支援協定を締結している。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
関西広域連合広域防災局
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県危機管理部 防災支援課内
電話番号:078-362-9278 ファックス:078-362-9839広域防災局へのお問い合わせはこちら